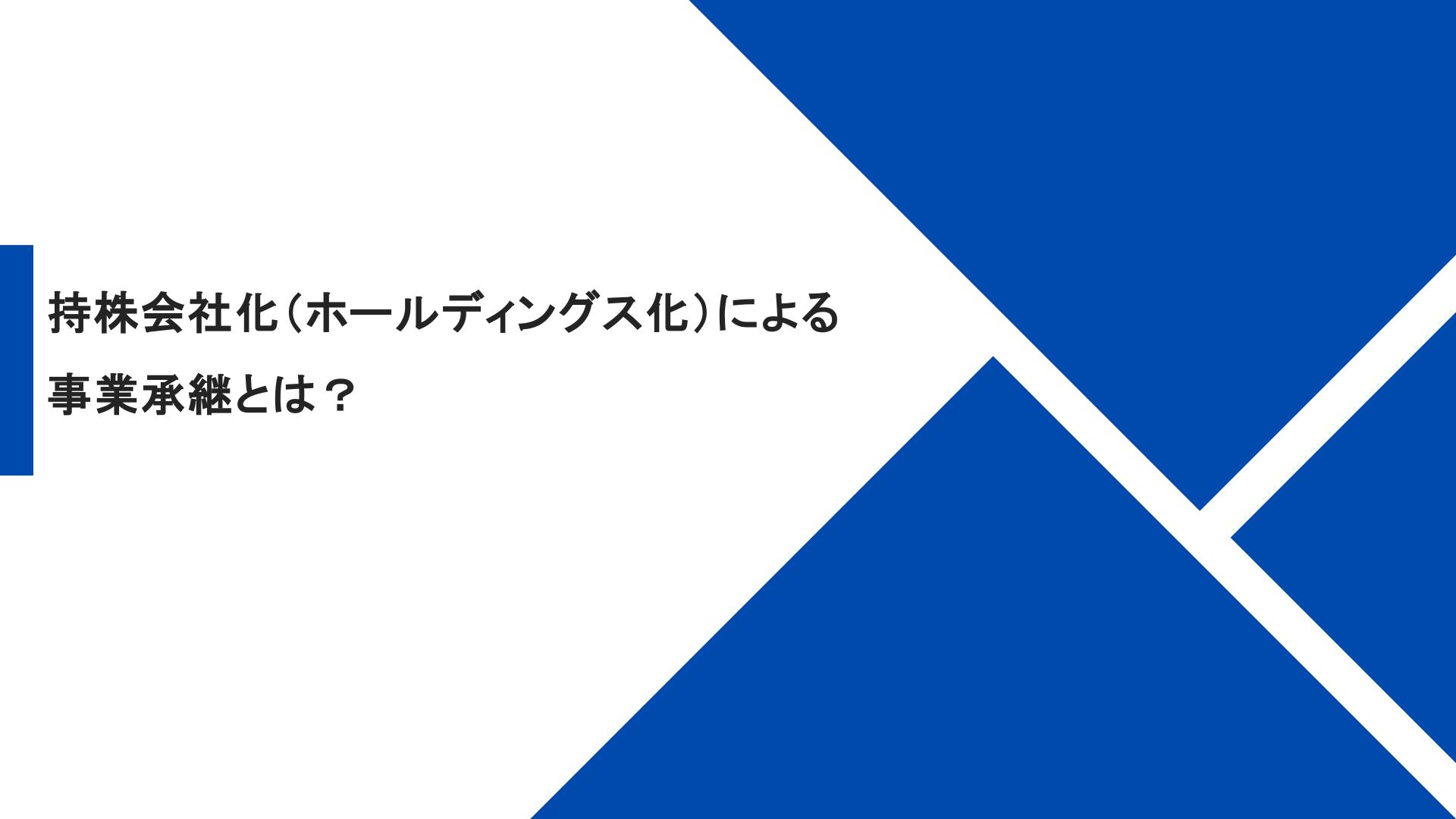
事業承継の手段の一つとして持株会社化(ホールディングス化)という手段があります。そもそも持株会社化とはどのように事業承継を行う方法のことを言うのでしょうか。
そこでこの記事では、持株会社化とはどんな手続きで事業承継を行う方法なのかに加え、持株会社化をすることによるメリット・デメリットについても解説します。
事業承継とは会社の経営を後継者に引き継ぐことを言います。特に中小企業においては後継者が見つからないことが現代において問題点となっており、後継者不足を解消するために中小企業庁が事業承継5カ年計画を提唱しています。
事業承継には様々な方法が存在しており、基本的には身内の中に後継者を見つける親族内承継、親族内に事業に関する知識がある人がいない場合などに行う従業員などへの承継、そして経営が苦しく、他の企業と合併することで事業を存続させるM&Aの3つのうちのどれかの方法で行われることが多いです。
持株会社とは、傘下の会社の株式を所有することで事業活動を支配することを目的に設立される会社のことを言います。
大型商業施設など様々な事業を展開しているイオングループを例に見てみましょう。この場合、イオン株式会社が持株会社となり、その傘下にコンビニエンスストア事業にあたるミニストップ株式会社や、都市小型食品スーパーマーケットであるまいばすけっとなどが存在しています。
持株会社は傘下にある会社の株式を取得し、その配当で運営されることが多いです。
持株会社は大きく分けると3種類存在します。
まず持株会社の中で最も多いのが純粋持株会社です。純粋持株会社は事業活動を行わないで、株式を獲得することで得られる配当のみで運営されています。イオン株式会社も純粋持株会社にあたると言えるでしょう。
次に純粋持株会社と違って自社でも事業を行いつつも、傘下にある会社を支配する事業持ち株会社が挙げられます。事業持株会社で有名な企業が少ないですが、例としてはシチズンが有名です。シチズンではシチズン時計株式会社がトップとなり、傘下の会社の経営を支配しつつも、時計の開発・製造・販売を行っています。
最後に金融持株会社です。金融持株会社は銀行や証券会社を支配することを目的とした持株会社であり、三井住友フィナンシャルグループや三菱UFJフィナンシャルグループが有名と言えるでしょう。
持株会社化をすることにはたくさんのメリットが存在します。まず、持株会社化をする場合、株式の移転がスムーズに進みます。
持株会社化をする場合、株式移転方式・株式交換方式・抜け殻方式の3種類が存在します。
株式移転方式は、新しい会社を設立してその会社を親会社とし、その会社に株式を移転させるだけなので簡単です。
次に株式交換方式はすでに存在している2つの会社が株式を交換し、一方が親会社、もう片方が子会社となります。この方法はM&Aの際に使われることが多いです。
そして抜け殻方式は親会社となる会社が子会社に事業を譲渡するなどして手続きを行います。そのため、純粋持株会社を設立する際に使われることが多いです。
このようにどの方法を採用しても持株会社化なら手続きがシンプルと言えるでしょう。
次に持株会社化は事業承継の際の税金対策にも良いです。 持株会社を設立し、既にある会社の株式を持株会社に売却したとします。そうすると、自社株が現経営者のものではなくなるので、現経営者の相続財産から外れることとなり、事業承継の際に発生する相続税がなくなります。
それに、事業承継によって持株会社が株式を保有することとなるので、株価も下がります。 事業承継をする際、贈与税や相続税など高額な費用が掛かります。しかし、持株会社化をすることで税金をかからなくしたり、自社株の株価を下げたりすることで、事業承継の際にかかる費用を少なくすることができます。
それ以外にも、複数のジャンルの事業を行っていた場合、傘下に食品系企業や家電系企業などジャンルごとの子会社を立ち上げることで事業を分散することができます。会社を運営していると、1つの事業が上手くいっても他の事業が上手くいかないために倒産してしまうことが多いです。そこで持株会社化をすることで、失敗した事業があったとしても他の事業に影響を及ぼす心配がなくなります。
持株会社化はメリットばかりではないことを理解しておかなければいけません。
まず、持株会社を経営する場合、会社を維持するためのコストが高くついてしまいます。傘下の企業はそれぞれ1つの会社として独立しているので、人事や総務、経理など事務系の部門が重複しやすいです。
しかし、これらの部門は企業の経営に欠かせない部門であり、しっかりこれらの部門も管理しなければいけません。したがって、持株会社化をした場合は事務系部門の規模が拡大した際に維持コストを縮小することが大切と言えるでしょう。
次に、持株会社と事業会社の連携が難しい点もデメリットと言えます。基本的にグループ経営とは言え、経営方針は傘下にある会社に自由に任せることが多いです。しかし、傘下の会社の経営を放置していると、持株会社と事業会社の連携が出来なくなってしまいます。場合によっては事業会社同士で対立してしまうこともあります。
そうならないように、持株会社と事業会社の間で良好な関係を築かなければいけません。 しかし、持株会社と事業会社の間で上下関係が生まれやすいです。
そこで事業会社の経営が悪くなっても持株会社に赤字を隠して経営が厳しくなってしまうという可能性も考えられます。そうならないようにもすべての事業会社に目を向け、程よい統制を行うことが必要でしょう。
持株会社化にはメリットもデメリットもあります。そのため、事業承継をする際に持株会社化を選択肢の一つとして考えておくのも良いですが、持株会社化にこだわりすぎないようにしましょう。 ただ、複数の事業を営んでいる場合や、相続税を安く抑えたい場合に持株会社化は便利な方法と言えます。
しっかり会社の現状をみてメリットとデメリットを比較し、事業承継をするにあたって持株会社化が最も良い方法なのかを考えたうえで実行しましょう。